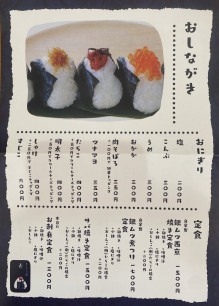【日大板橋病院から健康情報】肺がんはがん死因のトップ! 肺がんから命を守るために今すぐやるべきこと
日大板橋病院 日本呼吸器学会専門医 清水哲男先生からの健康情報

提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部
日本大学医学部附属板橋病院の医療専門家が、地域の皆さまに役立つ健康情報を発信。健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。
今回は「肺がん」をテーマに、日大板橋病院 日本呼吸器学会専門医 清水哲男先生に話をしていただきました。
肺がん死亡者数を減らすために:禁煙と早期発見の重要性
日本ではがんにより年間約40万人が亡くなり、がんは日本人の死亡原因の中で最も多い病気となっています。その中でも肺がんは毎年7万人以上が命を落としており、がんによる死因の1位です。肺がんの罹患(りかん)率(=新たに発生したがん患者の割合)は大腸がん、胃がんに次いで3位ですが、死亡者数が罹患率を大きく上回るのが肺がんの特徴です。
肺がんにならないための一次予防:生活習慣の改善が重要
肺がんによる死亡者数を減らすには、まず肺がんになりにくい体質を目指した生活習慣の改善、いわゆる「一次予防」が重要です。がんは喫煙、飲酒、塩分摂取、肥満などの生活習慣と深く関わっており、中でも喫煙が肺がん発症に最も強く影響します。
たばこを吸わないこと、すでに喫煙している方は禁煙に取り組むことが肺がん予防の第一歩です。受動喫煙も肺がんのリスク因子であるため、たばこの煙を避ける生活を心がけることが推奨されます。

二次予防:がん検診で早期発見を目指す
次に重要なのは、がんの「二次予防」としての定期的ながん検診です。二次予防とは、「がんにかかってしまった場合」の対策、つまりがんを早期に発見し治療することを言います。肺がんは他のがんと比べて初期症状が出にくく、進行が速いため早期発見が難しいという特徴があります。
肺がん検診は、40歳以上を対象に年1回、問診と胸部エックス線検査を行います。さらに、50歳以上で喫煙指数(1日の平均喫煙本数×喫煙年数)が600以上の方には喀痰(かくたん)細胞診が追加されます。
肺がん検診で発見された患者さんは、咳や血痰(けったん)、胸痛、息切れといった症状が出てから診断された患者さんと比べて治療成績が良く、予後も良好であることが分かっています。
低すぎる検診受診率、精密検査受診率の低さが大きな課題
一方、肺がん検診には課題も存在します。日本のがん検診受診率は50%台にとどまり、欧米と比較して低い水準にあります。また、肺がん検診で要精密検査と判断された方のうち、実際に精密検査を受ける割合(精検受診率)は約80%で、2割の方が精密検査を受けていないのが現状です。
早期治療を行えるよう要精密検査と診断された患者さんは、速やかに医療機関を受診しましょう。

肺がん死亡者数を減らすための3つのポイント
がんによる死因1位である肺がんを防ぐために、以下の3つを実践しましょう。
- たばこを吸わない(禁煙する)
- 毎年、肺がん検診を受ける
- 検診で要精密検査と判断された場合は速やかに精密検査を受ける
肺がん検診についての詳細は、お住まいの市区町村や職場の健康診断を通じて確認してください。がん検診と生活習慣の見直しが、肺がん予防の第一歩となります。

日本大学医学部附属板橋病院 日本呼吸器学会専門医 清水哲男先生
地域の健康を守る!「日大健康広報プロジェクト」

このプロジェクトは、大学病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信し、健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。
(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)