【日大板橋病院からの健康情報】怖い「膵臓がん」-早期発見のために今できる最善策
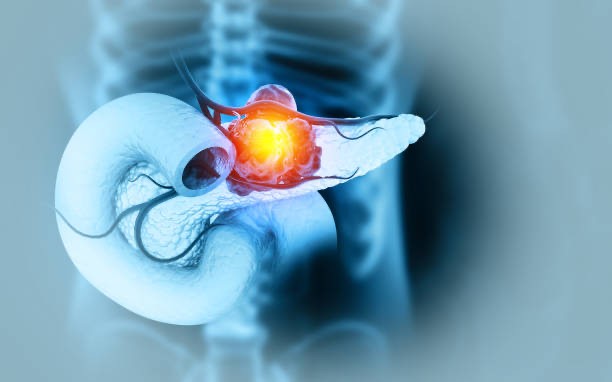
提供:日本大学医学部附属板橋病院 制作:板橋経済新聞編集部
日本大学医学部附属板橋病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信。健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。
今回は「膵(すい)がん」をテーマに、日本大学医学部附属板橋病院 消化器・肝臓内科 齋藤圭先生にお話をしていただきました。
1. 膵がんの早期発見は可能か?
膵がんと聞いて、皆さんはどのように感じるでしょうか。「症状がない」「進行してから発見される」「他のがんに比べて、たちが悪い」といった言葉が一般的で、多くの人にとって恐ろしい病気という認識があると思います。これらの言葉は膵がんの特徴を的確に表しており、医療者の言葉で言い換えると、「早期発見が難しい」ということになります。
膵がんは進行が速く、周囲の重要な血管や臓器に浸潤しやすいため、切除手術が可能な患者は全体の約20%に過ぎません。手術ができない場合、抗がん剤や放射線療法に頼ることになりますが、これらの治療法では膵がんに対して限られた効果しか期待できません。抗がん剤治療が進歩したことで、一部の患者はがんが縮小して外科的切除が可能になることもありますが、まだ限定的です。従って、根治可能な膵がんを見つけるためには、早期発見が非常に重要です。
2. 膵がんになりやすい人は?
膵がんの早期発見には、リスクが高い人に適切な検査や健康診断を受けてもらうことが不可欠です。では、どのような人が膵がんのリスクが高いのでしょうか?
膵がんのリスク因子には「喫煙」「肥満」「飲酒」といった生活習慣のほか、「糖尿病」「膵のう胞」「慢性膵炎」といった病歴があります。また、「家族歴」「特定の遺伝子異常」もリスク要因として重要です。例えば、喫煙者は非喫煙者と比較して約2倍の確率で膵がんを発症しやすいことが分かっています。肥満や糖尿病も膵がんとの関連が明らかにされており、膵がんのリスクは1.5~2倍程度になるといわれています。糖尿病は食生活の西洋化や運動不足、高齢化の影響で日本でも増加している病気です。膵臓は血糖を調整するインスリンを分泌する器官であり、インスリンが正常に働かなくなる糖尿病と膵がんは深い関係があります。

また、健康診断で見つかる「膵のう胞」も膵がんリスクとして非常に重要です。特に膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)は膵がんのリスクがあり、定期的な検査が推奨されています。IPMNは膵管内で粘液を産生する腫瘍で、粘液が蓄積して膵管が拡張するのが特徴です。この状態は腹部超音波検査やCT、MRIなどの画像検査で確認できます。中でも「主膵管型」は悪性化のリスクが高く、切除治療が推奨されます。一方、健康診断で発見されることが多い「分枝型」はすぐに手術が必要なケースは少ないものの、膵がんのリスクが2~10%程度あるため、半年に1回程度の画像検査が推奨されます。

3. 検診や定期検査を受けましょう
膵がんのリスクについて説明しましたが、特に強調しておきたいのは、糖尿病で治療を受けている人や、健康診断で膵のう胞が見つかった人は膵がんのリスクが高い可能性があるため、定期検査や詳しい検査を受けることが重要だという点です。かかりつけ医から「定期検査を受けましょう」と言われても、実際に検査を受けていない人も少なくありませんが、それでは膵がん早期発見のチャンスを逃してしまう可能性があります。ぜひ、しっかりと検査を受けてください。
膵がん早期発見のために有効な検査の一つが超音波内視鏡検査です。この検査は胃カメラの先端に超音波装置を搭載した特殊な内視鏡を用い、胃や十二指腸から膵臓を詳細に観察します。一般的な検査ではなく総合病院や大学病院でしか行われないことが多いですが、膵がんリスクが高いと判断された患者に対して行われることがあります。

4. 地域全体で膵がんを早期発見する取り組み
膵がん早期発見は、医療者にとっても重要な課題の一つです。地域全体の医療機関が協力して取り組むことが効果的な対策となります。各医療機関で情報共有を行い,紹介体制を整えることで,膵がんの早期発見につながります。かかりつけ医や健診で提案された際には、ぜひ検査を受けてください。

日本大学医学部附属板橋病院 消化器・肝臓内科 齋藤 圭先生
地域の健康を守る!「日大健康広報プロジェクト」

このプロジェクトは、大学病院の医療専門家が地域の皆さまに役立つ健康情報を発信し、健康的な生活をサポートすることで、地域全体の健康状態の向上を図ることを目的としています。
(転載・取材に関するお問い合わせ先:med.kouhou@nihon-u.ac.jp)















































