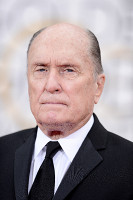東京での活動を担う板橋ママに聞いた 子育て中がメリットになる「赤ちゃん先生」の活動とは?
赤ちゃんが「先生」になって学校や施設を訪問する「赤ちゃん先生プロジェクト」という活動が全国で行われている。兵庫県で設立されたママ支援団体が、「女性が産後も働くことを通じて社会とつながっていける場を作りたい」という思いで始め、共鳴する全国のママたちがその輪を広げている。板橋区内の小学校でも今年初めて開催された。東京での活動を担うママに活動の魅力を聞いた。
「赤ちゃん先生プロジェクト」は、「先生」である赤ちゃんとママが教育機関や高齢者施設に訪問し、出産育児の話をし、赤ちゃんとの触れ合い体験を通じて、参加者に命の尊さや生きる喜びを伝えるもの。NPO法人「ママの働き方応援隊」(鹿児島県奄美市)が「子育て中がメリットになる働き方をつくる」ことを目標に掲げ、2007(平成19)年に同プロジェクトを始めた。今は全国各地のママたちが、それぞれの地域で活動を展開している。赤ちゃんが「先生」になれるのは0~3歳。訪問先とママとの仲介や授業をサポートする「トレーナー」という役割もある。教育機関などに出向き、開催を提案し、ママと赤ちゃんが活躍する場をつくる。有意義な活動になるよう、ママ向けに研修も行う。トレーナーは子どもの年齢に関係なく活動でき、ママと赤ちゃん、そして児童・生徒に貴重な体験を提供できるよう尽力している。
ママの働き方応援隊の東京支部長を務めるのは、板橋区のキャリア支援団体「マム・スマイル」代表の坂東愛子さん。3年前に、面識があったママの働き方応援隊の代表から東京支部での活動を打診されたのがきっかけ。坂東さんは「子育ては尊いものなんだと気づかせてくれる、とてもすてきな活動を多くの人に広めたい」と、すぐに応じたという。
メンバーはトレーナーが各エリアで募集している。坂東さんもマム・スマイルのメンバーに呼びかけたところ、数組のママと赤ちゃんが手を挙げた 。

2025年2月には板橋区立志村第三小学校(清水町)で初めて「赤ちゃん先生」を開催した。これまで都内のさまざまな教育機関で開いていたが、区内の小学校では初めてだったという。坂東さんの子どもが通っている学校でもあり、自分の子どもにも受けさせたいという思いが以前からあった。コロナ禍でしばらく活動できなかったが、昨年夏、福井みどり校長に打診するとすぐに承諾を得られた。普段から体験授業の学びに力を入れているため、快く受け入れてくれたという。校長からは「命の大切さや自分たちは愛されて育ってきたんだということを学んでほしいので、赤ちゃんとの触れ合いと育児の話を中心に」と要望された。
実際の授業では、児童たちが赤ちゃんに興味津々で、抱っこしたり、一緒にハイハイをしたりする姿が見られた。泣いている赤ちゃんをあやそうとする児童もいた。ママたちから赤ちゃんの授乳やおむつ替えの回数を聞くと、児童たちは驚いていた。命を守り育てる実際の話を聞いて、ここまで育ててくれた家族に感謝の気持ちを話した児童もいた。20分という短い時間ながら、「児童の成長が感じられ素晴らしい時間だった」と福井校長は振り返る。普段の学校生活では友人に乱暴な言葉遣いをしている児童も、赤ちゃんの前では自然と優しい口調になった。この様子を見た福井校長は感動したという。「赤ちゃん先生だからこそできる授業を開催できて本当に良かった」と坂東さんも笑顔で振り返る。
全国的に小学校では道徳の単元で開催し、2年生だけが対象になることが多いが、福井校長は「せっかくなら全学年で行いたい」と申し出てくれたという。今後、2~3年かけて全学年と赤ちゃんが交流する計画も検討されている。坂東さんは「自分の子どもも赤ちゃんと触れる機会ができる。どんな様子が見られるのか保護者としても楽しみ。自ら運営しているマム・スマイルのメンバーが子どもを連れて『先生』をしてくれることもうれしい」と話す。

活動に参加しているママたちは特別なことはしていない。自身の妊娠、出産体験と普段している子育ての話を児童・生徒に伝えている。妊娠・出産は女性のキャリアに大きな影響をもたらし、社会との距離ができやすい。しかし、ここではその経験こそがメリットになる。社会と離れがちで孤立しやすい乳幼児のママたちが、この活動で社会とのつながりを持てる。ママたちは社会で必要とされる場所を見つけたことで自己肯定感が高まり、普段の育児にもポジティブに向き合える。自分の子どもが大勢から歓迎され、うれしい気持ちにもなる。
「開催中のママたちを見ていると、子どもと一緒に楽しそうに参加をしている様子が伺え、この活動をさらに広げていきたいと思える。『赤ちゃん先生』としては子どもが3歳までしか活動できないが、トレーナーは子どもの年齢に関わらず活動できる。トレーナーとしてママたちが活躍する場を見いだせることにも意義を感じる」と坂東さん。活動の場を提供するトレーナーは、開催先への働きかけとして行政や教育機関に行く機会もある。日常では味わえないことを経験し、自分自身の成長や自己実現ができる。「自分の子どもが小学生になった時に、子どもの授業で『赤ちゃん先生』を開催させてあげられる喜びがあるのでトレーナーになる人も多い」とも。
祖父母が遠方にいる赤ちゃんも少なくないため、赤ちゃんが高齢者と関わる機会が減っている。電車内や店内で赤ちゃんが泣くと肩身の狭い思いをするママもいる。坂東さんは「乳幼児から幅広い世代の人々と関わることによって人格が豊かになる。子どもを産み、育てることは社会に良い影響をもたらすことをママ自身が知ることで、子育ての尊さを体感してもらいたい」と期待を込める。