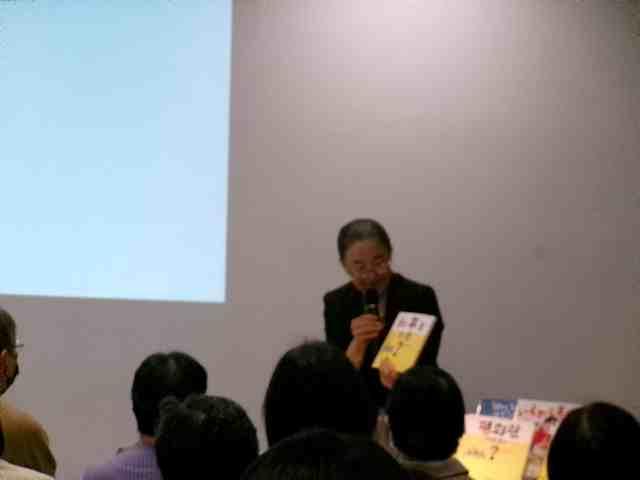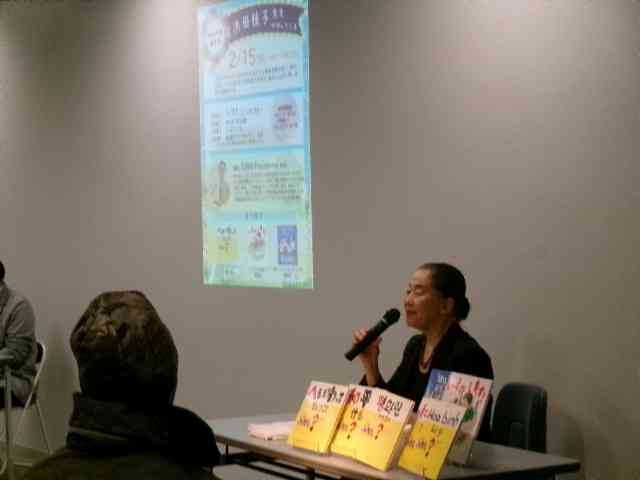中小企業でも可能にする男性育休 タニタハウジングウェアの取り組み
昨今、育児休暇を利用する男性は珍しくなくなってきている。しかし、まだまだ中小企業では男性育休が取りにくいのでは? そこで、男性の育児休暇が取得しやすく、「子育てサポート企業」として高い評価を受けている「タニタハウジングウェア」(板橋区東坂下2)を取材して、その理由を探った。
板橋区東坂下に本社を構える「タニタハウジングウェア」は創業78年。屋根の雨水を地面の排水管まで導く金属雨といのメーカーで、その分野ではトップシェアを誇る。社員125人(男性=85人、女性=40人)の中小企業である。

タニタハウジングウェア本社
2012(平成24)年、男女が共に働きやすい職場環境に取り組む中小企業などを表彰する「いたばし good balance 会社賞」を受賞。2017(平成29)年には厚労省からも優良な「子育てサポート企業」として「プラチナくるみんマーク」の認定を受けた。「男性育休」も推進しており、2022年には、営業職の男性が3カ月の育休を取得。現在も営業職の男性が11カ月の育休を取得中である。

「雨のみちをデザインする」。この言葉は社長が就任する2004年に発表。当時はあまり受け入れられなかったが、10年たってやっと根付いてきた感じがするというエピソードも。
なぜ、男性育休が取りやすいのか。その理由は、創業時にまでさかのぼる。谷田泰社長の祖父が事業を始めた1947(昭和22)年ごろ、東北などから親元を離れ寮生活をして働いている社員も多かった。そのため、社員というより家族の関係に近かったという。それだけに体調や健康管理を気遣う文化が昔から根付いていたという。谷田社長は「私が入社した約30年前から、自身の体調や家族の体調が悪い時は、『早く帰ってあげて』と言い合う文化があった」と振り返る。

(左から)谷田泰社長と総務の矢野さんと堀川さん
同社で初めて育児休暇の申し出があったのは、法改正で「産後パパ育休」が導入された2022年で、営業職の男性社員だった。制度を社員に周知するため、谷田社長はその男性社員と、育休取得前と取得後に対談し、その動画はユーチューブにもアップした。
男性は、2人目の子どもの時に育児休暇を取得。育休前の動画の中で育児休業を決めた理由として、妻から「1人目の時は初めての育児ですごく大変だった。それと同時に新生児の変化は日々すごく多く、その貴重な期間を共有できなかったのが残念。2人目の時は一緒にその時期を過ごしたい」と言ってもらったのが大きかった、と語っている。さらに、「義理の兄が1年間育休を取っているのも見ていたので、育休に対するいいイメージもつきやすかった」と話す。「育休取得に対する不安も少しはあったが、上司や同僚がみんな『いいじゃん』とポジティブな反応だったのでありがたかった」とも。
復帰後の動画で男性は「育休は本当に取って良かった」と話している。生後すぐに赤ちゃんの呼吸が不安定で、大きな病院に転院し、家族全員ナーバスになりやすい状況だったが、「支え合いながら乗り越えられた」という。幸いすぐに退院でき、家に帰ってからも、自分自身も「手伝い」ではなく、主体性を持って育児・家事に臨めたという。「2人の子どもだから2人で育てるということを体感できた3カ月だったし、復帰してからもその感覚は残り続けている」と男性は動画で語っている。
谷田社長も男性に、「育休が家族にとっていい時間になって良かった」「これから育休取得に対して不安や困っている社員がいれば相談に乗ってあげてほしい」と語りかけていた。
さらに今年5月から、営業職の男性が11カ月の育休を取得中。当初、1年近い育休の申し出に総務の担当者は少し驚いたそうだが、直属の上司が「今のはやりだし、最先端」と意欲的だったという。同社では、育休期間中も基本的に代替人員を立てず、既存のメンバーに仕事を振り分けている。育休中の社員の仕事をサポートするメンバーには手当を支給するようにもなった。手当の支給は、もともと就業規則にあったのではなく、現場の声を受けて採用し、就業規則にこれから追加していくという。
育休の取得でキャリアが一度断たれてしまうのではないかと不安に感じる社員も多いのではないだろうか。同社では、3年ほど前から「キャリアカウンセリング」にも力を入れている。年1回の面談でカウンセラー役となるのは管理職。特別に外部講師も入れてカウンセリング技法を学んでいる。カウンセラーは面談を受ける側が自由に選ぶことができ、社長との面談を選んだ社員も何人かいたという。キャリアカウンセリングを通して、「家族がいる上で、どういうキャリアを築いていきたいか」を考えていく時間になっているという。
制度が整っていても、実際に取得できるかどうかは職場の雰囲気や上司・同僚の理解が大きなカギを握っている。制度に加えて、普段から休みを取りやすくなる雰囲気づくりに取り組み、制度の発信・周知で実際の利用者の声や社長の温かい言葉によって、「本当に取得して大丈夫なんだ」という安心感が感じられる同社。これからのキャリアはどうありたいかと一緒に考えてくれる丁寧なサポートが、男性社員の背中をそっと押している。こうした土壌があるからこそ、中小企業でありながらも長期の男性育休が実現できている。