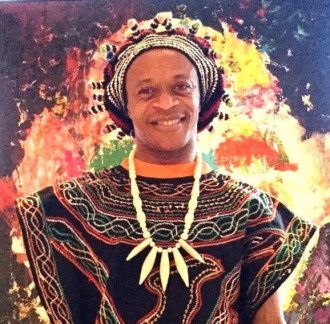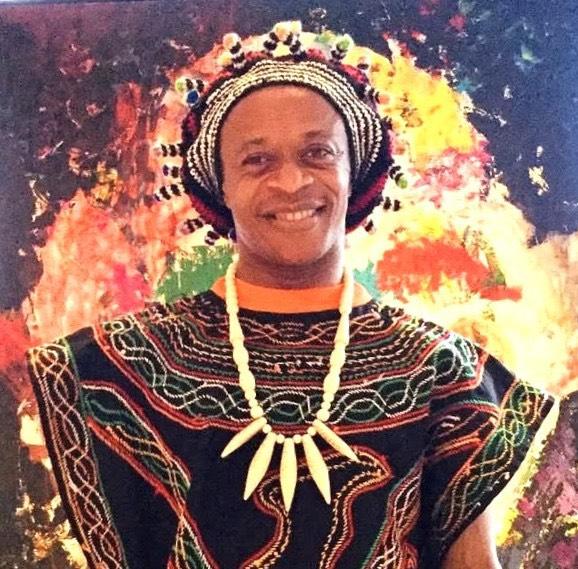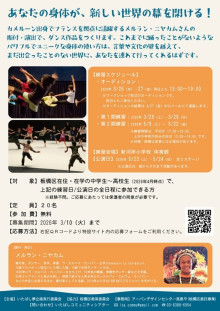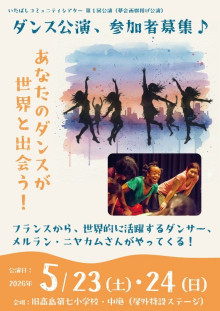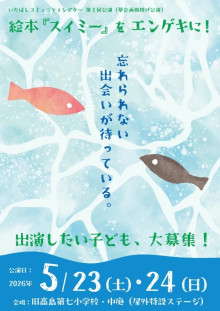東武東上線板橋区・ときわ台駅に漂う「香るアロマ」 込められた鉄道会社の思いとは
東武東上線のときわ台駅には甘酸っぱい香りが充満している。香りの元は、周辺に生えている樹木からでも近隣の店からでもない。東武鉄道が芳香器を使ってアロマの芳香を放っている。なぜ、駅にアロマなのか。そこには、少しでも鉄道事故を減らしたいという鉄道会社の思いがあった。
 ときわ台駅に設置されている芳香器(ディフューザー)
ときわ台駅に設置されている芳香器(ディフューザー)
「板橋の田園調布」を象徴する駅
同駅の北口改札を通り、ホームへ向かうための階段を下りると、かんきつ系の香りがふわりと匂う。風が強い日や電車が駅を通り過ぎるときには、ホームまで香りが巻き上がる。芳香器が設置されているのは地下通路の壁で、あまり目立たない。そのため、アロマの存在を知らない利用客も多い。
同駅は1935(昭和10)年、「武蔵常盤台駅」として開業した。当時、都市計画を担っていた内務省も関わる住宅地開発の中に位置づけられ、立ち並ぶ高級住宅街と、その街の形から「板橋の田園調布」とも呼ばれた。今の「ときわ台駅」に改称されたのは1951(昭和26)年。
今では1日約4万3000人が利用し、そのうち6割近くが通勤や通学客。駅周辺には飲食店が軒を連ねている。一方、鉄道事故が多い区間でもあった。2007(平成19)年には踏切内に立ち入った女性を助けるために、隣接する常盤台交番の巡査が殉職する痛ましい事故も起きた。
事故防止への取り組み
東武鉄道は鉄道事故を少しでも減らそうと、10年ほど前に事故防止対策の部署を設置し、さまざまな対策に取り組んできた。ホームドアの設置工事計画を進め、自殺防止のポスターをホームや線路沿いに掲示。ホームや踏切に青い電灯も設置した。青い光が精神状態を落ち着かせるといわれているため。「とにかくできることをしよう」という一念だったという。芳香器を設置したのは2014(平成26)年で、こうした対策の一つだった。現在設置している駅は、ときわ台駅を含め3駅。アットアロマ(世田谷区)の「ピースフルスマイル」という香りを使っている。
アットアロマによると「ピースフルスマイル」は、シトラスとハーブの穏やかな香りで、グレープフルーツ、カモミール、ベルガモットなどがブレンドされている。グレープフルーツやベルガモットは気持ちを明るく前向きにするといわれるかんきつの香りで、カモミールはストレスリラックス効果が期待されるという。アロマの効果については、大学の調査などでも「気分をポジティブにし、ストレスを緩和する」などの報告が行われている。
鉄道社員の思い、利用客の癒やしにも
駅員によると、時折、駅の利用客から「あのいい香りは何か」と問い合わせがあるという。あらゆるストレスがまん延する現代社会で、鉄道事故を減らすことはなかなか難しい。アロマの香りが実際にどれだけ事故の減少に効果的なのかを測ることも容易ではない。しかし、一つだけ確かなことがある。それは、乗客に少しでも前向きな気持ちで駅を利用してもらうために「できることは、何でもやってみよう」という東武鉄道の社員たちの強い思い。これにより、今もときわ台駅が甘酸っぱい香りに包まれている。そうした同社員の思いを全く知らない駅の利用客の心も、日々癒やしている。

上板橋駅ホームに設置されている青い電灯